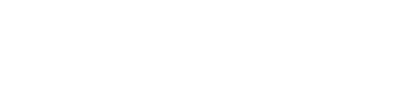「何をしても手足が冷たい」
「お風呂で一時的によくなっても、またすぐ冷えてくる」
「体温はあるのに寒く感じる」
こうした“冷え”の症状でお悩みの方は多く、特に女性に多くみられます。
しかし、単に「冷え性」と一括りにするだけでは、根本的な改善にはつながりません。
漢方では冷え性をいくつかの体質タイプに分けて捉え、それぞれに適したアプローチをおこないます。
この記事では、漢方の視点から見る冷え性の原因と体質別対策を解説しながら、日常生活でできる改善ポイントもご紹介します。
なぜ“冷え性”になるのか?|漢方の基本的な考え方
漢方医学では、体の状態は「気・血・水(き・けつ・すい)」の3つのバランスによって成り立っていると考えます。
冷え性は、これらのうちどれかが「不足」または「巡っていない」ことによって起こります。
西洋医学との違い
西洋医学では「末端冷え性」や「自律神経失調症」の一症状として扱われることが多く、対症的な治療が中心です。
しかし漢方では、“体の状態全体”を観察し、冷えがどこから来ているのかを深掘りして判断します。
漢方が考える「冷え性」4つの代表的な体質タイプ
① 気虚(ききょ)タイプ
エネルギー不足で体が温まらない
対策の方向性:補気(ほき)
→ 黄耆(おうぎ)や人参(にんじん)などの生薬がよく用いられます。
② 血虚(けっきょ)タイプ
血が不足し、温かさが行き渡らない
対策の方向性:補血(ほけつ)
→ 当帰(とうき)や芍薬(しゃくやく)などがよく使われます。
③ 瘀血(おけつ)タイプ
血が巡らず滞っている
対策の方向性:駆瘀血(くおけつ)
→ 丹参(たんじん)や桃仁(とうにん)、紅花(こうか)などの血に働く生薬を使用。
④ 陰証タイプ
体の“芯の火力”が低下している
対策の方向性:温
→ 附子(ぶし)や乾姜(かんきょう)などを中心に、じっくり温める処方が多いです。
その他の要因にも注目|“冷え”を深く読み解く
冷えのぼせ
下半身が冷えているのに、顔だけ火照るような症状。
「気の上昇」が背景にあることもあり、ストレスや自律神経の関与が疑われます。
瘀血タイプでも冷えのぼせがあります。
自律神経と冷えの関係
交感神経優位が続くと、末端の血管が収縮し血流が悪くなります。
これは、ストレス性の冷えや自律神経の乱れによる冷えとして現れます。
実はわたしもこのタイプです(^^)
冷え性改善のための漢方的セルフケア
養生のポイント
実際に漢方で冷え性が改善したケース
【40代女性:陰証+瘀血タイプ】
「お腹と下半身がいつも冷えてつらい」
→ 漢方と養生の併用で、3ヶ月後には腹部の温かさを実感。月経痛も軽減。
【30代女性:気虚+血虚タイプ】
「疲れやすく、寝ても元気にならない」
→ 補気補血の漢方と睡眠改善の指導で、2ヶ月後に冷えが和らぎ、顔色も良くなった。
※すべて個人の体験に基づく感想です。効果を保証するものではありません。
冷え性は“体からのサイン”|まずは体質を知ることから
冷えは単なる不快感だけでなく、将来的な不調や慢性症状の入り口にもなりえます。
体質に合わない対処では、かえって体を冷やしてしまうことも。
まずは自分の冷えのタイプを知り、正しく向き合うことが何より大切です。
お悩み解決の漢方相談はこちらから
→ 【LINE登録はこちら】 から、お気軽にご相談ください。
あなたの冷え、きっと改善できます。
🌿同じような症状でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
▶お問い合わせフォームはこちら
▶LINEでのご相談・ご予約はこちら
▶遠方の方のお手続きはこちら
▶初めての方へのご案内、Q&Aを見る
(効能効果には個人差がございます。当内容は同等の効果を保証するものではございません。あしからずご了承くださいませ。)